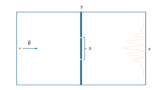はじめに
あまり意味がないかもしれないが、ブログにありがちな1年書いてみて思ったことを適当に記述してみようと思う。このブログは収益化していないし、今後もする予定がない。SNSなども一切活用していないため、一方的に筆者が書きたいことを書くだけのサイトになっている。ブログを運営する上では全く参考にならない記事なので、徒然なるままに綴ったエッセーに過ぎないことは最初に注意しておく。
このブログ自体は2023年の7月に作成されており、2023年の7月9日に最初の記事”ギャンブルにおけるKelly基準”が投稿されている。しかし、最初はやる気が起きなかったのか、1年近く放ったらかしにしていた。定期的に書くようになったのは2024年の6月からであり、電子書籍の”複素関数とシュレディンガー方程式”を書き終わって、Amazonにアップロードした後、何となくやることが無くなってしまったことがきっかけだったように思う。
サイト紹介にも書いている通り、動機としては数学の本をそのうち書いてみたいということであるが、”多時間理論による量子力学”、”複素関数とシュレディンガー方程式”を書いて思ったことは、最終的に考えた結果だけがまとめられていて、なぜそう考えたかの過程が読者には分からないんじゃないかということだった。そのため、ブログの形でなぜそのように考えたかを記録していけば、将来的に完成した本の内容について、なぜそのような内容が書かれているのか知ることができるようになるだろうと考えた。
ただ、実際に書き始めると、興味が湧いた内容を好き勝手書くだけになってしまっており、ただの趣味のサイトになってしまっている感が否めない。それはそれでいい気もするので、今後もおそらくその方向性で内容を書いていくことになるだろう、数学の本はいつ書けるかわからないが、一応最後に今後の目標でどういった本を書くつもりか説明しておく。予定は未定であり、結局やらないかもしれないが、現時点の目標を書いておくことには一定の意味があるような気が・・・まあ、なくてもいいか。というわけで、ブログを書いてきた感想のようなものを書いていこう。
誰にも読まれない記事を書くことに慣れる
おそらくブログを始めた人の多くが経験することとして挙げられるのが、書いた記事のPV数(アクセスされた回数)が0の日が数か月は続くということである。時々アクセスされる日もあるが、検索エンジンのクローラーと言われるプログラムであり、人間が読んでいるものではないことがほとんどである。この期間は最もやる気が挫かれる期間だろう。せっかく書いた文章が誰からも読まれないということで、ブログを始めた人のほとんどはこの期間中にやる気をなくして辞めてしまうのではないだろうか。
SNSなどを使って呼び込みを行わない場合、ブログにアクセスされる経路はほぼGoogleなど検索エンジンの検索結果からであるが、最初の数か月は検索結果の上位に自分のページが表示されることはほとんどない。検索エンジンが検索結果の上位に表示する基準として、投稿されている記事の数なども考慮されているらしく、記事の数が少ない状態だと検索結果に表示されるかの順位争いで不利になるということらしい。しばしば指摘されるのが、記事の件数や量が大事であるから、最初の3か月ぐらいはPV数は気にせず、ひたすら記事を書きまくれ、最低でも100件は書けというものである(ちなみに、このブログはまだ100件に到達していない)。
このブログもやはり同様の現象が生じており、2024年の6月から9月までの4か月近くはほとんどアクセスされていない。急速にアクセス数が伸びたのが2024年の10月からであり、投稿数が30を超えたあたりからだった。この辺りから、Googleの検索結果で上位に表示される記事が出るようになってきた。誰にも言わずこっそり書いていたが、知り合いにブログを書いていることが知られるという事態が起こったのも2024年10月頃である。筆者はあまり気にしていなかったが、ほぼ誰からも読まれない記事を数十件の単位で書かなければならないということで、これはそういうものだという知識を持っておかないとやりきれないかもしれない。
ただ、やっているうちに誰にも読まれない記事を書くことにも慣れてくるように思う。筆者の場合、収益化を目的にしていないので、読まれるか読まれないかは本当のことを言うとどうでもいいのかもしれない。読まれる記事より書きたい記事が優先であり、最近の誰得な感じの作曲記事などは完全に筆者の興味で書かれていて、実際全く読まれていない。全く読まれないから意味がないかというと、そういうわけでもないし、(可能性は低い気がするけど)そのうち読む人も出てくるのかもしれない。
こういった現象はブログに限らず、音楽や動画、ゲーム開発などでも同様のことなのかもしれない。作成しているコンテンツが認識されるようになるには時間がかかるということであり、誰も見ない期間であっても、制作活動を続けることが必要になるのだろう。後述するが、筆者は音楽は始めたばかり、ゲーム開発は今後やってみようと考えているが、誰も聞かない音楽、誰もやらないゲームを制作する期間を持つことになりそうである。重要なのは、他人が見るかやどう評価するかより、自分が作りたいかどうかを優先した方が良いということだろう。
PV数が多い記事ランキング
ブログの中でアクセス数多いランキングを5位まで示しておこう(2025年7月15日時点)。
1.調和振動子とシュレディンガー方程式
2.オブジェクト指向でわかる神の存在証明
3.m HOLD’EM(エムホールデム)の攻略方法
4.ベッセル関数
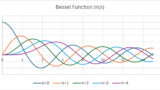
5.複素数の正規分布
1位は”調和振動子とシュレディンガー方程式”であり、Google検索でも上位に表示されるページである。大学生が勉強のために見ることが多そうなページであるが、残念ながら、このページはそういった大学生の要望に応える内容になっていない。量子力学の教科書では、シュレディンガー方程式をユークリッド空間上に定義された方程式と考えて議論されるが、実はシュレディンガー方程式は球面(相対論的な空間)上に定義された方程式であり、それを勘違いしているために調和振動子と間違って理解しているという筆者の批判的な意見を書いたページになっている。
2位は”オブジェクト指向でわかる神の存在証明”というエキセントリックなタイトルのページである。ゲーデルの神の存在論的証明を、オブジェクト指向の概念を使ってパロディ的に説明しているのが主な内容である。ためになる内容ではないかもしれないが、ゲーデルの神の存在論的証明が直感的にどういう論理で構成されているか理解できるように書かれているだろう。タイトルが目を引きやすいことにも原因があるのかもしれない。
3位は最近のこのブログで飛びぬけてアクセス数を稼いでいるページであり、ソーシャルゲームのエムホールデムの攻略記事になっている。近いうちにこのページのアクセス数が筆者のブログの中では1位になりそうである。攻略記事と書いたが、正確にはなぜ筆者がエムホールデムで勝てないのかという言い訳を書いているページということで、攻略できない理由を説明した内容になっている。エムホールデムは不思議なテキサスホールデムのゲームで、ポーカーの本に書かれているような戦略を用いるとなぜか勝てないのであるが、その理由を考察している。
4位、5位は正直言って筆者には想定外であり、こんな記事が読まれるのかと不思議になった記事である。ベッセル関数の初等的な知識をまとめたページと2変数の正規分布を強引に複素数として扱った場合の確率分布の議論である。いずれも筆者的にはメモ書き程度のつもりだったが、コンスタントにアクセスされるページになっている。
読まれているページについて書いてきたが、反対に筆者としては自信作であり、これは読まれるだろうと思っていたのに、読まれていない記事を3つぐらい挙げておこう。特に、二重スリット実験は筆者が自信を持っている内容だったのだが、なぜかあまりアクセスされていない。読まれるか、読まれないかは検索エンジンの上位に表示されるかに依存する部分もあるので、二重スリット実験の記事は世の中にたくさんあるために、筆者のページが上位に表示されていないのかもしれない。
今後の目標
最後に、とりあえず今考えている今後の目標を述べておこう。この半年ぐらいのブログの傾向からわかるように筆者は現在テキサスホールデムに強い関心を寄せている。ゲームとしての面白さももちろんであるが、主な関心事はテキサスホールデムの数学的な側面である。数学の本を1冊書くことを目標にしていると書いてきたが、テキサスホールデムの数学的な理論を記述した電子書籍を将来的に書いてみたいと考えている。
テキサスホールデムは機械学習やゲーム理論、意思決定理論(ギャンブル理論)などと強い関係があるが、計算技術としてモンテカルロシミュレーションや統計学、ベイズ推定なども応用できるゲームだろう。こういった内容を筆者流に統一感を持った形で1冊の本として記述するというのが現在考えている目標である。
これに当たって、統計モデルや機械学習を使ったNPCのモデルを開発して、モバイルゲームなどの形態で(iPhoneやAndroidで)プレイできるゲームを開発したいと考えている。要するに、数式だけで説明されても何のことだか理解しづらいだろうから、本とモバイルゲームの内容をリンクさせてみようということである。電子書籍で説明されるこの数学の理論がゲームのNPCのモデルのこの部分に用いられているとか、ゲームのルールを変則的にした時の最適な戦略を求めるのに電子書籍のこの理論を応用して求めることができる、などの説明ができれば面白くなるんじゃないかと思う。
また、現在作成している音楽はゲームのBGMとして利用することを考えている。電子書籍、ゲーム、音楽といった複数の作品を総合的に提供する形態が良いのではないかと考えている。もちろん、作らなければならないものは膨大になるが、生成AIを活用することである程度のレベルでは達成できるのではないかと期待している。1年後にどの程度の内容が達成されているかはわからないが、現時点では特にやる気も衰えていないので、多少なりとも意義のあるコンテンツが作成できるのではないだろうか。