古典力学における等速円運動
3次元空間における等速円運動を考える。古典力学において等速円運動のエネルギー(ハミルトニアン)は
\[ \small E = H(p,q) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2r^2 \]
で与えられる。単純化のため、円運動の回転方向は\(\small xy\)平面とし、\(\small z=0\)と仮定する。加速度を計算すれば
\[ \small \begin{align*} &-\frac{\partial H}{\partial x} = m\frac{d^2x}{dt^2} = -m\omega^2x \\ &-\frac{\partial H}{\partial y} = m\frac{d^2y}{dt^2} = -m\omega^2y \\ &-\frac{\partial H}{\partial z} = m\frac{d^2z}{dt^2} = -m\omega^2z=0 \ \end{align*} \]
となる。これらの微分方程式を満たす一般解は無数にあるが、特殊解として
\[ \small \begin{align*} &x(t) = r\cos(\omega t) \\ &y(t) = r\sin(\omega t) \\ &z(t) = 0 \end{align*} \]
を選択する。\(\small r=\sqrt{x^2+y^2}\)は定数であると仮定しよう。
この運動について、速度や運動量、角運動量をそれぞれ求めよう。速度は
\[ \small \begin{align*} &v_x = \frac{dx(t)}{dt} = -r\omega\sin(\omega t) = -\omega y(t) \\ &v_y = \frac{dy(t)}{dt} = r\omega\cos(\omega t) = \omega x(t) \\ &v_z = \frac{dz(t)}{dt} = 0 \end{align*} \]
である。したがって、
\[ \small v = \sqrt{v_x^2+v_y^2+v_z^2} = r\omega \]
を得る。したがって、角速度\(\small \omega\)は
\[ \small \omega = \frac{v}{r} \]
と定めることができる。運動量は
\[ \small \begin{align*} &p_x = m v_x = -mr\omega \sin(\omega t) = -m\omega y(t) \\ &p_y = m v_y = mr\omega \cos(\omega t) = m\omega x(t) \\ &p_z = m v_z = 0 \\ &p=\sqrt{p_x^2+p_y^2+p_z^2} = mr\omega \end{align*} \]
となる。角運動量を計算すると
\[ \small \begin{align*} &l_x = yp_z – zp_y = 0 \\ &l_y = zp_x – xp_z = 0 \\ &l_z = xp_y – yp_x = m\omega r^2 \\ &L^2 = l_x^2+l_y^2+l_z^2 = m^2\omega^2r^4 \ \end{align*} \]
を得る。元のエネルギーの式に代入すれば
\[ \small E = \frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2r^2=\frac{L^2}{2mr^2}+\frac{1}{2}m\omega^2r^2=m\omega^2r^2 \]
となる。また、円周の長さは\(\small 2\pi r \)であるから、1周して元の座標に戻るまでの時間(周期)は
\[ \small vt = r\omega T = 2\pi r \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} \]
となる。
相対性理論における等速円運動
相対性理論の主張はどのような物質の運動も光速\(\small c\)を超えてはならないというものであり、相対論的な運動方程式において速度は運動量\(\small p\)を用いて
\[ \small \frac{dq}{dt} = \frac{p_\mu c}{\sqrt{m^2c^2+p^2}}, \quad q=x,y,z \]
と表せるというものであった。前回述べたように、これは近似計算で厳密には連立微分方程式を解かなければならないと推測されるが、ここでは近似計算の方で運動方程式を求める。
等速円運動における運動量は
\[ \small \begin{align*} &p_x = -mr\omega \sin(\omega t) \\ &p_y = mr\omega \cos(\omega t) \\ &p_z = 0 \ \end{align*} \]
であるから、相対性理論における速度の公式にこれを代入して運動方程式を求めればよい。代入すると
\[ \small \begin{align*} &\frac{dx}{dt} = -\frac{mr\omega \sin(\omega t) c}{\sqrt{m^2c^2+m^2r^2\omega^2}} = -\frac{r\omega \sin(\omega t) c}{\sqrt{c^2+r^2\omega^2}} \\ &\frac{dy}{dt} = \frac{mr\omega \cos(\omega t) c}{\sqrt{m^2c^2+m^2r^2\omega^2}} = \frac{r\omega \cos(\omega t) c}{\sqrt{c^2+r^2\omega^2}} \\ &\frac{dz}{dt} = 0 \end{align*} \]
を得る。
\[ \small v = \sqrt{v_x^2+v_y^2+v_z^2} = r\omega\frac{c}{\sqrt{c^2+r^2\omega^2}} \]
であるから
\[ \small \lim_{r,\omega\rightarrow \infty} v = c \]
であり、光速を超えることがないことが確認できる。運動方程式を求めるため、この式を積分すれば
\[ \small \begin{align*} &x(t) = \frac{rc}{\sqrt{c^2+r^2\omega^2}}\cos(\omega t) \\ &y(t) = \frac{rc}{\sqrt{c^2+r^2\omega^2}}\sin(\omega t) \\ &z(t) = 0 \end{align*} \]
と計算できる。これが相対性理論における等速円運動の運動方程式ということになる。この場合、円運動の半径は
\[ \small R = \frac{rc}{\sqrt{c^2+r^2\omega^2}} \]
であり、\(\small \omega\)を所与とすればその最大値は
\[ \small \lim_{r \rightarrow \infty} = R = \frac{c}{\omega}=\frac{\lambda}{2\pi} \]
で与えられることに注意する。\(\small \lambda\)は波動の用語でいうところの波長に対応するパラメータである。このように考えれば、光(光子)の性質を表すパラメータ(波長や振動数、波数など)は、等速円運動のような運動の性質を表現しているものと解釈することもできるかもしれない。
筆者が関心を抱いている仮説である相対論的な時空は円錐座標系
\[ \small x^2+y^2+z^2+c^2T_{xyzt}^2=c^2t^2 \]
で表され、局所時間\(\small T_{xyzt}\)(我々が時間として認識している概念。\(\small t\)は我々が認識している時間ではないことに注意。)は関数で表されるという説において、この場合における局所時間は
\[ \small T_{xyzt} = \sqrt{t^2-\frac{R^2}{c^2}} \]
となり、円運動上の座標において流れる時間は共通の値になっている。原点から離れるほど時間の進み方が遅くなることは式から明らかだろう。また、円周の長さは\(\small 2\pi R\)であるから、1周して元の座標に戻るまでの時間(周期)は速度を原点における時間\(\small t\)で測ると
\[ \small vt = R\omega T = 2\pi R \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} \]
となる。一方で、局所時間\(\small T_{xyzt}\)で測ると
\[ \small vT_{xyzt} = r\omega T = 2\pi R \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}\frac{c}{\sqrt{c^2+r^2\omega^2}} \]
となり、半径が小さくなっている分だけ周期が短くなる(光速に近づくにつれて、局所時間で測った時間の進みが遅くなる)と考えられる。
最後に、エネルギーを計算すると
\[ \small \begin{align*} E &= \sqrt{m^2c^4+p^2c^2}+\frac{1}{2}m\omega^2R^2 \\ &\approx mc^2+\frac{1}{2}m\omega^2r^2\left(1+\frac{c^2}{c^2+r^2\omega^2} \right) \end{align*} \]
となり、古典力学のエネルギーとは結果が(微小であるけど)乖離することが確認できるだろう。運動量の\(\small r\)と軌道半径の\(\small R\)が乖離することに原因があると考えられる。この節の計算は近似に過ぎないということだろう。前回の稿で厳密に計算するにはポテンシャルを2倍にしたうえで、エネルギーを
\[ \small E = \sqrt{m^2c^4+p^2c^2+\frac{1}{4}V^2}+\frac{1}{2}V \]
と定義しなければならないと記述した。上記に当てはめると
\[ \small \begin{align*} &p = mr\omega \\ &V(q) = m\omega^2r^2 \ \end{align*} \]
であり代入すると
\[ \small E = \sqrt{\left(mc^2+\frac{1}{2}m\omega^2r^2\right)^2}+\frac{1}{2}m\omega^2r^2=mc^2+m\omega^2r^2 \]
となる。このエネルギーが半径\(\small r\)の等速円運動を表すエネルギーいうことになる。この運動量とポテンシャルが表す運動方程式が
\[ \small \begin{align*} &x(t) = r\cos(\omega t) \\ &y(t) = r\sin(\omega t) \\ &z(t) = 0 \end{align*} \]
であるということだが、このエネルギー式からこれをどうやって導けばよいかは現在の筆者には不明である。ちなみに、ポテンシャルを2倍にして
\[ \small E = \sqrt{m^2c^4+p^2c^2+\frac{1}{4}V^2}+\frac{1}{2}V \]
などと書かず
\[ \small E = \sqrt{m^2c^4+p^2c^2+V^2}+V \]
と書けよと思うかもしれない。しかし、理論的に導出できる式が上の式であり、古典力学と相対性理論ではエネルギーから運動方程式を導出する方法が異なるため、このように記述しないと類似した運動方程式を導出できないということである。
任意の方向に回転する等速円運動
等速円運動というものが光(光子)の運動に関係ありそうだということを示したことで本稿の目的は達成されているが、3次元空間なのだから\(\small z=0\)などという仮定はいかがなものかという気もしてくる。等速円運動の議論を任意方向の回転にした場合にどうなるかも示しておこう。
詳細は省略するが、回転座標変換行列というのを掛ければ良いらしい。それは以下のようなものである。
\[ \small \left[ \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \end{array} \right] \left[ \begin{array}{ccc} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{array} \right] \left[ \begin{array}{ccc} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \]
それぞれ、\(\small x,y,z\)軸周りの回転を表す。\(\small z\)軸周りは位相(初期座標)の値を変えるだけ(\(\small \omega t\)を\(\small \omega t + \psi\)と置けばよい)であるから無視して計算すると
\[ \small \begin{align*} &x(t) = r\cos\theta \cos(\omega t)\cos \phi + r\sin \phi \sin(\omega t) \\ &y(t) = r\cos\theta \cos(\omega t)(-\sin \phi) + r\cos \phi \sin(\omega t) \\ &z(t) = r\sin\theta \cos(\omega t)\ \end{align*} \]
のように変形できる。\(\small \phi=\theta=0\)としたときに元の式になるように座標軸を入れ替えている。\(\small \theta,\phi\)の値を変えることで任意の方向に傾いた等速円運動を表現できるということである。
一応、速度や運動量、角運動量をそれぞれ求めておこう。速度は
\[ \small \begin{align*} &v_x = \frac{dx(t)}{dt} = -r\omega\cos\theta \sin(\omega t)\cos \phi + r\omega\sin \phi \cos(\omega t) \\ &v_y = \frac{dy(t)}{dt} = -r\omega\cos\theta \sin(\omega t)(-\sin \phi) + r\omega\cos \phi \cos(\omega t) \\ &v_z = \frac{dz(t)}{dt} = -r\omega\sin\theta \sin(\omega t) \\ &v = \sqrt{v_x^2+v_y^2+v_z^2} = r \omega \end{align*} \]
である。運動量は\(\small p=mv\)で計算すればよいだろう。角運動量を計算すると
\[ \small \begin{align*} &l_x = yp_z – zp_y = m\omega r^2\sin\theta\cos \phi \\ &l_y = zp_x – xp_z = m\omega r^2\sin\theta\sin \phi \\ &l_z = xp_y – yp_x = m\omega r^2\cos\theta \\ &L^2 = l_x^2+l_y^2+l_z^2 = m^2\omega^2r^4 \ \end{align*} \]
となる。このようにみると、角運動量を極座標のように変換すればよいのかもしれない。相対性理論の議論は\(\small r\)を
\[ \small R = \frac{rc}{\sqrt{c^2+r^2\omega^2}} \]
に置き換えれば同様に成立するだろう。



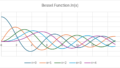
コメント