古典力学における自由落下
空気抵抗や摩擦の影響を無視した重力のみによる落下運動のことを自由落下(Free Fall)という。重力が働く場合のポテンシャルエネルギーは
\[ \small V=mr\frac{d^2r}{dt^2} = -\frac{GmM}{r} \]
と表すことができる。ここで、\(\small G\)は重力定数と言われる自然定数であり、\(\small m,M\)は二つの物質の質量、\(\small r\)は二つの物質の距離を表す。したがって、重力による加速度は
\[ \small \frac{d^2r}{dt^2} = -\frac{GM}{r^2} \]
である。地球のように非常に大きい物質から重力を受ける場合、\(\small M\)は地球の質量、\(\small r=R\)は地球の半径で近似できるため
\[ \small g = \frac{GM}{R^2} \]
が定数であると仮定する。\(\small 1/r\approx r/R^2\)と近似すれば、ポテンシャルエネルギー(地球の座標をマイナス方向に取るので符号が紛らわしいけど)は
\[ \small V = \frac{GM}{R^2}mr = mgr \]
と表すことができ、これが自由落下におけるポテンシャルエネルギーとなる(正確には、地球の表面からの距離を\(\small r\)と表すと
\[ \small V = \frac{GmMr}{R(R+r)} \]
である。)。
この場合における運動方程式を求める。
\[ \small \frac{d^2r}{dt^2} = -g \]
であるから積分すれば
\[ \small \begin{align*} &r(t) = -\frac{1}{2}gt^2 \\ &v=\frac{dr}{dt} = -gt \end{align*} \]
を得ることができる。初期時点の座標が\(\small r(0)=0\)となるように積分定数を定めている。エネルギーを計算すると
\[ \small E = \frac{1}{2}mv^2+mgr = \frac{1}{2}mg^2t^2-\frac{1}{2}mg^2t^2 = 0 \]
となる。これが古典力学における自由落下の運動方程式であった。
相対性理論における自由落下
地球上における自由落下で相対論的な効果が物質の運動に意味のある影響を及ぼすことはほとんどないため、相対性理論における自由落下の計算というのはあまり示されていない。一般相対性理論における等価原理の説明にはよく用いられるのに、なぜその計算結果が示されることがほとんどないのか不思議に感じるが、真面目に計算する価値がないように思れているからだろう。相対性理論における自由落下の運動方程式を示せと言われて、即座にこれを示せる人はあまり多くないのではないだろうか。ただ、古典力学が重力というものをいかに間違って理解しているかを簡単に示せる例と考えられるため、ここで簡単に計算してみよう。
相対性理論の主張はどのような物質の運動も光速\(\small c\)を超えてはならないというものであり、相対論的な運動方程式において速度は運動量\(\small p\)を用いて
\[ \small \frac{dr}{dt} = \frac{pc}{\sqrt{m^2c^2+p^2}} \]
と表せるというものであった。\(\small p\)が\(\small mc\)と比較して無視できるほど小さい場合
\[ \small \frac{dr}{dt} \approx \frac{p}{m} \]
であり、これが古典力学における運動方程式であった。
自由落下における運動量は
\[ \small p=m\frac{dr}{dt} = -mgt \]
であるから、相対性理論における速度の公式にこれを代入して運動方程式を求めればよい。代入すると
\[ \small \frac{dr}{dt} = -\frac{mgct}{\sqrt{m^2c^2+m^2g^2t^2}} = -\frac{gct}{\sqrt{c^2+g^2t^2}} \]
を得る。分母を\(\small c\)と近似すれば古典力学の式に一致することが確認できるだろう。また
\[ \small \lim_{t\rightarrow \infty} \frac{dr}{dt} = -c \]
であり、光速を超えることがないことが確認できる。運動方程式を求めるため、この式を積分して、\(\small r(0)=0\)となるように積分定数を定めればよい。計算すると
\[ \small r(t) = \frac{c}{g}\left(c-\sqrt{c^2+g^2t^2}\right) \]
と計算できる。これが相対性理論における自由落下の運動方程式ということになる。これも
\[ \small \sqrt{c^2+g^2t^2} \approx c\left(1+\frac{g^2t^2}{2c^2} \right) \]
と近似すれば、古典力学における自由落下の運動方程式と一致することが確認できるだろう。
ちなみに、上記の解は
\[ \small r^2-\frac{2c^2}{g}r-c^2t^2 = 0 \]
という二次方程式の解になっている。各座標\(\small r\)ごとに異なる時間が流れていて
\[ \small T_{rt}^2 = -\frac{2r}{g} \rightarrow r = -\frac{1}{2}gT_{rt}^2 \]
と定めると
\[ \small r^2+c^2T^2_{rt}=c^2t^2 \]
と表すことができる。時間という概念が関数\(\small T_{rt}\)というものとして定義できれば、この座標系が想定している時空は円錐座標系であると推測できるだろう。古典力学的な近似というのは\(\small T_{rt} \approx t\)に相当するということである。
加速度という概念は相対性理論と整合しない
古典力学では重力は加速度をもたらす力と考えられている。すなわち、座標の運動方程式で表せば\(\small t^2\)に比例する項として現れるという性質を持っている。しかし、相対性理論においては\(\small \sqrt{c^2+g^2t^2}\)であり、光速に近づくにつれて\(\small t\)に比例する項に近づいていくという性質を持つ。古典力学において二乗に比例すると考えられていた計算が、光速に近い運動を相対論的に計算すると一乗に比例する計算に近づくということがあるが、これはその計算の例になっているということだろう。
古典力学が重力をどのように間違えて理解しているかというと、実は加速度という概念は相対性理論と整合しない根本的に間違っている概念であるということに起因する。加速度という概念は空間がユークリッド空間で表せるという前提に依存するが、実際の空間の性質はユークリッド空間とは異なるものであるということになるだろう。この間違っている概念に基づいて重力という現象を理解しようとしているということが古典力学が多くの混乱を我々にもたらしている原因なのだろう。実際に、加速度から派生する力や仕事といった概念が相対性理論に登場することは全くと言っていいほどないだろうし、加速度という概念を用いずに重力などの現象を定義しなければならないというのが一般相対性理論の難しいところなのだろう。
相対性理論におけるハミルトニアン
第2節の相対性理論における自由落下の運動方程式を体系的に導出する方法はないか考えてみたのであるが、相対性理論におけるハミルトニアンを
\[ \small H(p,q) = \sqrt{m^2c^4+p^2c^2} + V(q) \]
とおいて、
\[ \small \begin{align*} &\frac{dq}{dt}=\frac{\partial H(p,q)}{\partial p} = \frac{pc^2}{\sqrt{m^2c^4+p^2c^2}} \\ &\frac{dp}{dt}= -\frac{\partial H(p,q)}{\partial q} \end{align*} \]
とすれば上記の計算になる。注意点はハミルトニアンの座標に関する微分は加速度にはならず、運動量の時間微分という意味合いしか持たないということである。加速度を求めたい場合は\(\small dq/dt\)をさらに\(\small t\)で微分して求めればよいだろう。
実際に、自由落下のケースを計算してみると
\[ \small H(p,q) = \sqrt{m^2c^4+p^2c^2} + mgr \]
から運動量を求めれば
\[ \small \frac{dp}{dt} = -\frac{\partial H(p,q)}{\partial q}=-mg \Rightarrow p(t) = -mgt \]
を得る。座標の式は
\[ \small \frac{dr}{dt}=\frac{\partial H(p,q)}{\partial p} = \frac{pc^2}{\sqrt{m^2c^4+p^2c^2}} = -\frac{gct}{\sqrt{c^2+g^2t^2}} \]
と計算できる。計算結果を式に代入すると
\[ \small \begin{align*} E &= \sqrt{m^2c^4+p^2c^2} +mgr \\ &=\sqrt{m^2c^4+m^2c^2g^2t^2}+mg\frac{c}{g}\left(c-\sqrt{c^2+g^2t^2}\right)=mc^2 \end{align*} \]
となり、一応エネルギーが保存量になっていることが確認できる。この場合エネルギーは
\[ \small (E-V)^2=m^2c^4+p^2c^2 \]
という式で表されるということになる。このような計算方法に正当性があるか、ただの近似でたまたま結果が合致しただけかは不明である。
実を言うと、筆者の意見は否定的であり、簡便的に光速を超えないように解を出せるものの、これは近似にすぎず、本来の相対性理論における保存量ではないと推測している。相対論的な時空を円錐座標系(空間を3次元球面)と仮定すると理論的な保存量\(\small E\)は
\[ \small E(E-V) = m^2c^4+p^2c^2 \]
を満たす値であり、その解は
\[ \small E = \sqrt{m^2c^4+p^2c^2+\frac{1}{4}V^2}+\frac{1}{2}V \]
となる。ハミルトニアンは
\[ \small H(p,q) = \sqrt{m^2c^4+p^2c^2+\frac{1}{4}V^2(q)} + \frac{1}{2}V(q) \]
となるだろう。平方根に含まれるポテンシャルは電磁気学や量子力学ではベクトルポテンシャルとして扱われ
\[ \small H(p,q) = \sqrt{m^2c^4+(p-eA)^2c^2} + \frac{1}{2}V(q) \]
と表現されていると考えられる。
また、相対性理論におけるポテンシャルは古典力学におけるポテンシャルの2倍であり、例えば自由落下の場合は
\[ \small V(q) = 2mgr \]
が相対性理論におけるポテンシャルになるだろう。この場合、正準方程式は
\[ \small \begin{align*} &\frac{dp}{dt}= -\frac{\partial H(p,q)}{\partial q} =ー\frac{m^2g^2r}{\sqrt{m^2c^4+p^2c^2+m^2g^2r^2}}-mg \\ &\frac{dr}{dt}= \frac{\partial H(p,q)}{\partial p}= \frac{pc^2}{\sqrt{m^2c^4+p^2c^2+m^2g^2r^2}} \end{align*} \]
となり、厳密な解はこの連立微分方程式を解かなければならないということになる。これは解析式で解くのが難しく数値計算で解かなければ厳密な解を得られないということになるかもしれない。最初に示したエネルギーを
\[ \small (E-V)^2=m^2c^4+p^2c^2 \]
と仮定する計算は、
\[ \small \begin{align*} &\frac{m^2g^2r}{\sqrt{m^2c^4+p^2c^2+m^2g^2r^2}} \approx \frac{mg^2r}{c^2} \approx 0 \\ &\frac{pc^2}{\sqrt{m^2c^4+p^2c^2+m^2g^2r^2}} \approx \frac{pc^2}{\sqrt{m^2c^4+p^2c^2}} \end{align*} \]
という近似をしており、ベクトルポテンシャルに相当する項を無視しているということだろう。
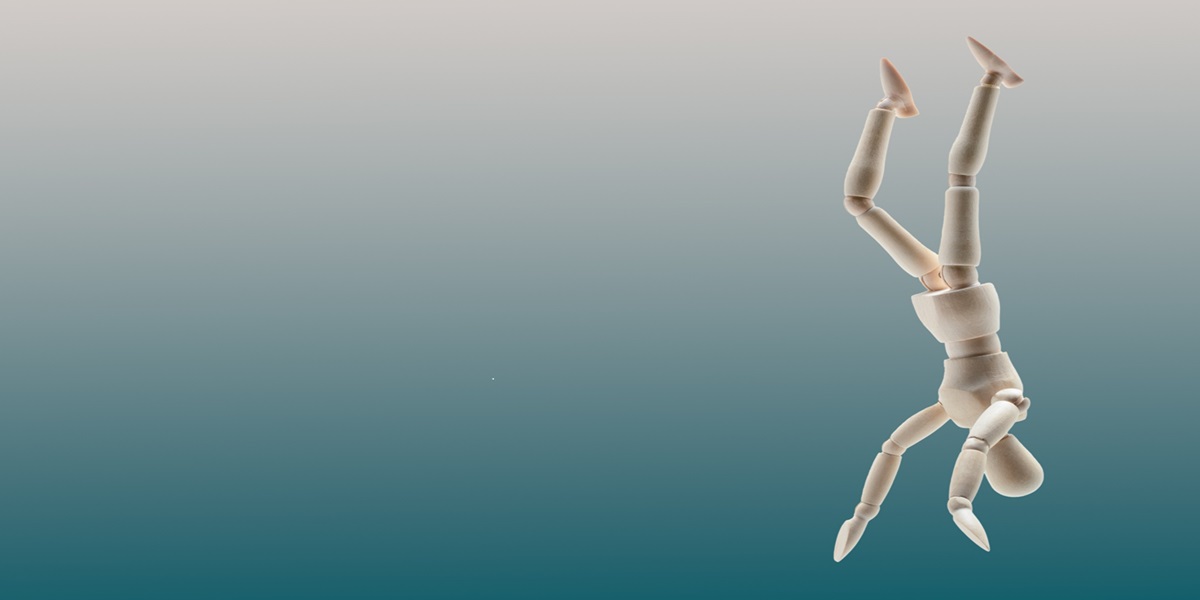


コメント